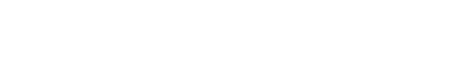令和6年1月1日より、電子取引データの電子保存が義務化された。対象となる取引情報は、「取引に関して受領し、交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書、請求書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項」である。本記事では、電子取引の具体例と保存要件について詳しく解説する。
1.電子取引の具体例
電子取引の例としては、次のようなものがある:
- メールにデータを添付して送受信する場合
- ホームページからのデータダウンロード
- ホームページ上で表示された請求書や領収書のスクリーンショット
- クラウドサービスを利用したデータの授受
- クレジットカードの利用明細データをクラウドサービスで確認する場合
- EDIシステム(電子データ交換)やインターネットバンキング
- ペーパーレス化されたFAXの利用
2.電子取引データ保存の要件
電子取引データの保存には「(1)可視性の要件」と「(2)真実性の要件」を満たす必要がある。以下にそれぞれの要件について説明する。
(1)可視性の要件
電子取引データの保存時には、検索機能の確保やシステム概要書の備付け、見読可能装置等の備付けが必要となる。備付けの要件については、通常のPC等で保存し、ディスプレイ、プリンタを備え付けていれば、その要件を満足する。
①検索機能の確保
電磁的記録を保存する場合、以下の検索機能を確保する必要がある:
- 日付、金額、取引先で検索可能であること
- 日付や金額の範囲指定検索が可能であること
- 2以上の項目を組み合わせた検索が可能であること
<一覧表の作成により、「検索機能の確保」を行う具体例>
・ファイル名には1、2、‥‥と通し番号を入力する。
・エクセルの一覧表に、通し番号、日付、金額、取引先を入力する。
<MFクラウドBOXにデータをアップロードすることにより、「検索機能の確保」を行う具体例>
授受区分(受領、発行)、書類種別(請求書、契約書など)、取引日、取引先名、金額、を登録する。
②検索機能が不要となる場合
検索機能の確保が一部または全部不要となる特例がある。
イ:一部不要
保存義務者が国税に関する法律に基づく提示・提出(ダウンロード)の求めに応じられる場合、以下が不要:
- 範囲指定検索
- 組み合わせ検索
ロ:全部不要(その1)
以下の条件を満たす場合、検索機能の確保が完全に不要:
- 基準期間における売上高が5000万円以下
- ダウンロードの求めに応じられる状態である。
ハ:全部不要(その2)
以下の条件を満たす場合、検索機能の確保が完全に不要:
- 整然とした形式の書面出力が可能で、取引日や取引先ごとに整理された形で提示できる。
- ダウンロードの求めに応じられる状態である。
「ダウンロードの求め」に関して、税務調査の際に税務職員が確認可能な状態で提出されるのであれば、電磁的記録の形式や並び順は問われないが、通常出力可能なファイル形式等で提供する必要がある。
また、税務職員が要求する電子データを短時間で提供できることを意味する。さらに、税務職員の求めの全てに応じた場合をさし、その求めに一部でも応じない場合は、条件を満たしていないこととなる。
(2)真実性の要件
電子データは改ざんや消去が容易なため、「真実性の要件」を確保するための措置が求められる。以下の方法のいずれかを選択して対応する必要がある。
・タイムスタンプの付与:送信者側または受信者側でタイムスタンプを付与する。
・訂正削除履歴が残るシステムの利用:データの授受と保存が訂正削除履歴が残るシステムで行われること。
・事務処理規程の制定:不当な訂正や削除を防ぐための事務処理規程を定め、これを遵守する。
システム費用等がかからないため、「事務処理規程の制定」が最も容易と考えられる。事務処理規程の雛形が、国税庁ホームページに掲載されており、参考となる。
3.猶予措置(令和6年1月1日以後)
所轄税務署長が「相当の理由」があると認める場合には、上記(1)、(2)の保存時に満たすべき要件に沿った対応が不要となる。単に電子データを保存しておけばよい。
以下のような事情がある場合に、「相当の理由」があると認められる。
・システムや社内のワークフローの整備などが間に合わない場合
・資金繰りや人手不足などの理由で要件に沿った保存ができない場合
この猶予措置では、税務職員からの電子取引データの「プリントアウトした書面の提示・提出の求め」に加え、「ダウンロードの求め」に応ずる必要がある。
なお、単に経営者の信条のみに基づく理由である場合は、「相当の理由」に該当しないことに留意が必要となる。