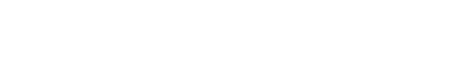令和7年度税制改正大綱が公表され、法人版事業承継税制における役員就任要件が緩和されることとなった。
これまで、先代経営者から後継者に非上場株式等を贈与する際、贈与税の納税猶予を適用するには、次の要件を満たす必要があった。
- 後継者が「贈与の日まで引き続き3年以上、承継する会社の役員であること」
この要件のため、令和9年12月31日が期限の贈与税の納税猶予を受けるためには、後継者は令和6年12月31日までに役員に就任することが求められていた。
令和7年度税制改正では、役員就任要件が以下のように変更された。
- 改正後:「贈与の直前において、承継する会社の役員であること」
これにより、後継者が令和7年1月以降に役員に就任しても、納税猶予の適用が可能だ。計画の自由度が高まり、円滑な事業承継が期待される。
なお、令和9年12月31日の適用期限は、今後とも延長しない旨、過年度の税制改正大綱に引き続き明記されている。
また、事前の計画策定が求められており、特例承継計画の提出期限は令和8年3月31日までとなっており、適用期限よりも早いため注意が必要だ。
贈与税の納税猶予及び免除
法人版事業承継税制とは、先代経営者から後継者が非上場株式等を贈与により取得した場合、一定の要件のもと、贈与年分の贈与税額のうち、その非上場株式等の価額に対応する税額の納税を猶予されるものである。
その後、先代経営者の死亡により、猶予された贈与税額は免除されることとなる。
以下は、後継者が贈与時に満たすべき主な要件である。
- 贈与時点で18歳以上であること
- 会社の代表権を有していること
- 後継者及びその親族の議決権の合計が50%超であること
- 後継者の親族内で議決権の筆頭者であること
- 贈与の直前において承継する会社の役員であること(令和7年度税制改正後)
- その他一定のもの
以下は、先代経営者が満たすべき主な要件である。
- 先代経営者の親族内(後継者除く)で議決権の筆頭者であったこと
- 贈与時において会社の代表権を有していないこと
また、会社についても、上場会社でないこと、風俗営業会社でないこと、資産保有型会社で一定のものでないこと等の要件が求められる。
先代経営者死亡時 相続税の納税猶予及び免除
先代経営者の死亡により贈与税は免除されるが、非上場株式等は、先代経営者の相続税の課税対象の財産とみなされる。
そのため、非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の規定により、後継者の相続税額のうち、非上場株式等の価額に対応する税額の猶予を受ける必要がある。
最終的に後継者が死亡した時点において、猶予された相続税が免除となる。
ここでの留意点として、「他の相続人が取得する財産」に課される相続税への影響である。
相続税の計算における非上場株式等の価額は、贈与時の価額を用いられる。
後継者の非上場株式等の取得について相続税は猶予されるが、他の相続人が納める相続税は、この非上場株式等を含めた相続財産の合計額に応じた超過累進税率に基づき、最大で55%の税率が課される。
非上場株式等の贈与時の価額に関して、十分な引き下げ対策を行わなければ、相続財産の合計額が大きくなり、税率が引きあがる。すなわち、「他の相続人が取得する財産」に課される相続税が大きくなるので注意が必要だ。
納税猶予の取消しのリスク
納税猶予の適用後も、継続的な届出書の提出が必要である。以下のスケジュールに従い、期限内に適切に提出を行わない場合、猶予が取り消される可能性がある。
- 最初の5年間:毎年提出
- 6年目以降:3年に一度提出
万が一、猶予が取り消された場合、猶予されていた税額と利子税を一括納付する必要がある。
後継者の非上場株式等の取得に係る贈与税と相続税は、後継者が死亡した時にようやく全て免除される。
この意味合いを掘り下げると、後継者のさらに次を引き継ぐ世代の存在まで求められる。
わかりやすくいうと、先代経営者(父)、後継者(子)、後継者の次を引き継ぐ世代(孫)という親族関係である。
後継者に次を引き継ぐ世代がいないのであれば、生涯現役という場合を除き、後継者は生前に親族外の第三者に引き継ぐこととなる。
M&A等により第三者に、非上場株式等を譲渡した場合、やはり納税猶予が取り消され、納税が必要となる。
いずれにしても、法人版事業承継税制は、納税猶予及び免除と、一見聞こえはよいが、先代経営者から後継者への贈与時のみならず、先代経営者の死亡時、後継者の死亡時まで、様々な要件と手続きが求められるため、この適用にあたっては、相当の時間をかけて検討することが求められる。