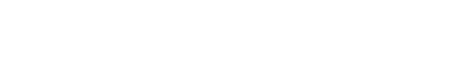認知症などにより意思能力を失うと、契約締結などの法律行為が無効となるケースがある。その影響は個人の財産管理にとどまらず、会社経営にも重大な影響を及ぼす。
認知症が会社経営に及ぼすリスク
代表取締役が意思能力を失った場合、会社名義で締結した契約も、契約時点で代表取締役本人が意思能力を欠いていれば、事後的に無効とされるリスクが生じる。また、代表取締役の解任も簡単ではない。中小企業の場合、経営者自身が主要な株主であることが一般的であり、株主総会での解任決議が難航する可能性が高い。
さらに、株主権を行使する株主自身に意思能力がない場合、その株主権の行使自体が事後的に無効とされるリスクがある。
法定後見制度の限界
意思能力を失った後では、家庭裁判所に申し立てて成年後見人を選任する法定後見制度が利用できる。ただし、成年後見人が選任されるまでに3か月程度を要することがあり、その間に会社経営が停滞する可能性がある。さらに、成年後見人が後継者や親族などになるとは限らず、家庭裁判所が選任した第三者が後見人となるケースも多い。このため、成年後見人が議決権の行使や経営判断を本人と同じレベルで行うのは難しく、現実的に経営に支障をきたすことが多い。
事前対策としての属人的株式の活用
認知症リスクに備えるため、事業承継対策を事前に講じることが重要だ。株式の譲渡や贈与には時間や資金が必要であり、組織再編や株価引き下げ策を検討しても即座に実行できない場合がある。これらの手続きでは多額の納税負担が生じる可能性もあるため、計画的な資金準備が必要となる。そのような状況で検討すべき対策の一つが属人的株式の導入だ。
属人的株式とは
属人的株式とは、定款によって株主ごとに議決権を異なる内容で設定できる株式のことだ。たとえば、後継者が1株を所有していれば、次のような定めを定款に記載できる。
「後継者Aは、株主オーナーBについて以下の事由が生じた場合、その有する株式数を問わず、当会社の総議決権の3分の2の議決権を有する。
- 成年後見、保佐または補助が開始され、もしくは株主オーナーBを成年被後見人とする任意後見契約が効力を生じたとき。
- 介護保険で要介護2以上の認定を受けたとき。」
このような規定を設けることで、後継者が経営権を確保しやすくなる。
属人的株式の導入手続き
属人的株式を導入するには、株主総会で特殊決議を行う必要がある。特殊決議は以下の要件を満たすことが求められる。
- 総株主の半数以上の賛成
- 総株主議決権の4分の3以上の賛成
定款への記載は必要だが、登記は不要となる。
まとめ
認知症などの意思能力喪失リスクに備えるには、属人的株式の導入が有効な手段となる。定款の変更や株主総会の特殊決議を早めに行い、事業承継や経営権の安定化を図ることが重要だ。適切な対策を講じることで、会社経営の混乱を最小限に抑えることが可能となる。