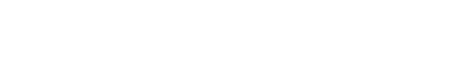令和6年(2024年)から、相続税法の課税制度が大きく変わる。特に、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の違いについて理解しておくことは、相続対策において非常に重要となる。本記事では、これら2つの制度の違いと、それぞれのメリット・デメリットについて詳しく解説する。
1.暦年課税制度と相続時精算課税制度の基本的な違い
1-1. 暦年課税制度の変更点
令和6年から、暦年課税制度において贈与財産を相続財産に加算する期間が3年から7年に延長された。これにより、相続対策で贈与を行ったとしても、相続時には贈与財産が加算される期間が長くなる。
ただし、相続開始前7年間の内、改正により延長された4年間分の贈与については、総額100万円までは相続財産に加算されない。
1-2. 相続時精算課税制度の新たな基礎控除
一方、相続時精算課税制度では、年間110万円の基礎控除が新たに設けられた。この控除を利用すれば、贈与税の支払いなしで、相続財産に加算する必要もなく、毎年最大110万円までの贈与が可能だ。相続時精算課税制度の特徴は、贈与財産のうち110万円を控除した残額だけを相続財産に加算すればよい点である。
2.暦年課税制度と相続時精算課税制度の具体例
2-1. 暦年課税制度の具体例
暦年課税制度において、相続開始前7年間に毎年110万円の贈与を行った場合、相続財産に加算される贈与財産の額は次のようになる:
- 110万円 × 7年 - 100万円(控除額)= 670万円
2-2. 相続時精算課税制度の具体例
相続時精算課税制度を選択した場合、相続財産に加算される贈与財産は次のように計算される:
- 110万円 × 7年 - 110万円 × 7年(基礎控除額)= 0円
このように、相続時精算課税制度では、毎年、基礎控除額110万円の範囲で贈与を行った場合、相続財産に加算される金額はゼロとなる。
3.相続時精算課税制度を安易に選んではいけない理由
3-1. 相続時精算課税制度の適用条件と注意点
相続時精算課税制度は、贈与者が60歳以上、受贈者が18歳以上である場合に選択適用が可能だ。適用を受けることで、相続税の節税が期待できるが、この制度を安易に選択することにはリスクがある。
最も大きなリスクは、「相続時精算課税制度を選択した年から、すべての贈与財産(基礎控除額を除く)が相続財産に加算される」点だ。また、一度この制度を選択すると、後から暦年課税制度に戻すことはできない。
3-2. 早期適用のデメリット
日本人の平均寿命は、男性が81.05歳、女性が87.09歳(令和4年時点)である。贈与者が60歳で相続時精算課税制度を選択すると、20年~30年間にわたる贈与(基礎控除額を除く)が全て相続財産に加算される可能性があるため、慎重な検討が必要となる。
4.相続税調査におけるリスク
4-1. 暦年課税制度の調査対象
暦年課税制度では、相続開始前7年間の贈与が相続税の調査対象となり、それ以前の贈与については相続税とは切り離される。したがって、7年を超える過去の贈与が相続税に影響を与えることはない。
4-2. 相続時精算課税制度と税務調査
相続時精算課税制度の場合、相続開始前7年間だけでなく、それ以前の贈与も含めて、税務当局により調査される可能性がある。現行法では、銀行・証券会社の取引記録の保存期間は10年だが、将来的に保存年限が延長されることも考えられる。そのため、相続時精算課税制度を選択する際は、税務調査のリスクを十分に理解しておくことが重要となる。
5.まとめ:暦年課税と相続時精算課税の選択
暦年課税制度と相続時精算課税制度の選択は、贈与者の状況や相続計画によって異なる。特に、相続時精算課税制度は一度適用すると撤回できないため、慎重に選ぶ必要がある。また、相続時精算課税を選択することで、税務調査に対するリスクが増えることを理解し、適用するタイミングや方法について十分な検討を行うことが求められる。
贈与税や相続税の対策については専門家に相談し、自身のライフプランに最適な選択をすることが重要だ。