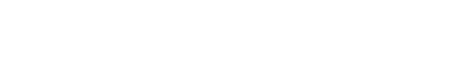令和6年(2024年)からの税制改正により、相続税の計算が大きく変わる。生前に行った贈与財産を相続財産に加算する期間が、これまでの相続開始前3年間から7年間に延長された。この変更は、相続税対策を行う際に大きなポイントとなる。
1.贈与財産の加算期間延長と節税効果
相続税の対策として、親から子への生前贈与が一般的に行われる。しかし、この加算期間の延長により、これまでよりも節税効果が低くなる可能性がある。
相続開始前7年間に贈与を行った場合、その贈与財産は相続財産に加算して相続税を計算する必要があるからだ。これにより、生前贈与のタイミングや方法に慎重な検討が求められる。
本記事では、この税制改正後もなお効果のある相続税対策として、贈与税の非課税規定や、その他の加算されない贈与について解説する。
※ なお、相続開始前7年間の内、改正により延長された4年間分の贈与については、総額100万円までは相続財産に加算されない。
2.贈与税の非課税規定を活用した節税
贈与税には、非課税となる贈与があり、これらの贈与については相続税の計算時に相続財産に加算する必要はない。これを活用すれば、相続税対策として非常に有効だ。
2-1. 扶養義務者から被扶養者への贈与
例えば、扶養義務者が被扶養者に渡す生活費や教育費は、非課税とされている。具体的な例としては、祖父母から孫への教育資金が挙げられる。以下の贈与が非課税の対象となる:
- 入学金
- 授業料
- 通学定期代
- 学習塾やピアノのレッスン料
- 留学のための旅費 など
ただし、「通常必要と認められるもの」として規定されており、都度使い切る必要がある。つまり、教育費を貯蓄することは認められない。
2-2. 教育資金の一括贈与非課税措置
孫の将来を見越して前倒しで贈与を行いたい場合、教育資金の一括贈与に関する非課税措置を活用することができる。この場合、最大1,500万円まで非課税で贈与が可能だ。
ただし、近年の税制改正により、平成31年4月以降の贈与については、贈与者(祖父母等)が死亡した時点で、未使用の残額を相続財産として加算される規定が設けられた。贈与者の死亡時に、受贈者が23歳未満である等一定の要件を満たせば、加算の必要はない。
さらに、令和5年4月以降の贈与については、贈与者(祖父母等)の相続税の課税価格が5億円を超えると、受贈者が23歳未満等であっても、未使用の残額を相続財産として加算されるので注意が必要だ。
贈与前には、相続財産に加算する可能性があるか否か検討を行うことが必要となる。
| 贈与時期 | H25.4~H31.3 | H31.4~R3.3 | R3.4~R5.3 | R5.4~R8.3 |
| 相続財産への加算 | 加算なし | 死亡前3年以内の贈与に限り加算あり※1 | 加算あり※1 | 加算あり※2 |
※1:受贈者が、23歳未満、学校等に在学、教育訓練を受講中の場合には、加算なし。
※2:受贈者が、23歳未満、学校等に在学、教育訓練を受講中の場合には、加算なし。ただし、相続税の課税価格が5億円を超えるときは、加算あり。
3.孫への贈与と相続税対策
祖父母から孫への贈与は、相続税対策として非常に有効な方法だ。贈与財産を相続財産に加算する期間は7年間だが、相続人となる子ではなく、孫に対する贈与は相続税に加算する必要はない。
ただし、以下のケースでは、孫への贈与財産を相続財産に加算する必要があるため注意が必要となる:
- 祖父母の死亡よりも子が先に死亡した場合
- 孫が死亡保険金の受取人となる場合
- 孫を養子とする場合
- 遺言書により孫に財産を取得させる場合
これらのケースでは、孫が相続人又は受遺者として扱われ、贈与財産が相続税の対象となる可能性がある。したがって、贈与を行う前に十分な検討が必要だ。
4.まとめ:贈与税制改正と効果的な相続税対策
令和6年の税制改正により、贈与財産の相続財産への加算期間が7年間に延長された。この変更により、早期に贈与を行っても、相続税の節税効果は低くなる可能性がある。しかし、贈与税の非課税規定や、教育資金の一括贈与、子ではなく孫への贈与などを活用することで、引き続き効果的な相続税対策は可能だ。
生前贈与を行う際は、贈与税の非課税枠や、贈与後の相続税への影響をしっかりと理解した上で、慎重に計画を立てることが重要となってくる。