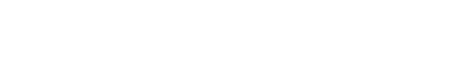相続が開始した際、被相続人の夫が老人ホーム等に入居していても、自宅の宅地評価を80%減額できる場合がある。この適用を受けるためには、以下の条件を満たしていることが必要だ。
STEP 1: 「夫の居住用の宅地」に該当するかを判定する
夫が老人ホーム等に入居しており、自宅に住んでいなかったとしても、次の条件を満たしていれば「夫の居住用の宅地」として評価額を80%減額することが可能。
- 要介護・要支援認定の必要性:夫が要介護認定、要支援認定、または障害支援区分の認定を受けていることが必要である。この確認には介護保険の被保険者証の写しや障害福祉サービス受給者証の写しなどが必要。
- 入居時の認定の有無:老人ホーム等の入居時に認定がなくても、相続開始時に認定を受けていれば問題ない。
- 老人ホーム等の要件:対象となる施設は、老人福祉法や介護保険法、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく一定の施設であることが条件。入居時の契約書などで確認が必要。
ただし、老人ホーム等の入居後に別生計の子が新たに自宅に住み始めた場合、「夫の居住用の宅地」としての適用は受けられない。例えば、妻の健康を案じて別生計であった子が同居するようになった場合などがこれに該当する。一方、老人ホーム等の入居前から妻や子が同居していた場合は問題ない。
なお、老人ホーム等への入居ではなく入院していた場合、自宅が他の用途に使われていない限り、「夫の居住用の宅地」として取り扱える。入院期間の長さは問われない。
STEP 2: 「同一生計の妻の居住用の宅地」に該当するかを判定する
「夫の居住用の宅地」に該当しない場合、次に「同一生計の妻の居住用の宅地」に該当するかを判定する。老人ホーム等に入居していることで夫と妻は別居状態だが、「同一生計」であるかどうかが重要なポイントとなる。
- 同一生計の判定基準:自宅の公共料金、固定資産税、妻の食費などを夫が負担していた場合、または妻が夫の老人ホーム費用や医療費を負担していた場合に「同一生計」と判定される。この場合、STEP 1とは異なり、別生計であった子が自宅に戻ってきても影響はない。
相続後の適用要件
STEP 1またはSTEP 2に該当し、妻が相続または遺贈によって自宅を取得した場合、宅地評価の80%減額を受けることが可能。他に要件はない。
一方、夫の入居前から同居していた子などの親族が、相続または遺贈により自宅を取得する場合は、相続税の申告期限まで、居住と所有を継続する必要がある。
いずれも、宅地80%減額の適用可能な面積は330㎡までであり、他の宅地も相続または遺贈される場合、面積限度に応じて調整が必要となることがある。
まとめ
夫が老人ホーム等に入居していても、条件次第で自宅の宅地評価を80%減額することが可能である。このような特例を利用することで、相続税の負担を大幅に軽減できる可能性があるため、条件をよく確認し、適切な対策を取ることが重要だ。具体的な条件や疑問がある場合は、専門家に相談して判断を仰ぐことを推奨する。