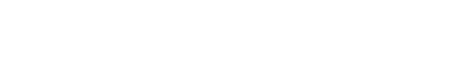配偶者居住権は、被相続人が死亡した後、残された配偶者の居住場所を確保しつつ、その後の生活費となる遺産も取得できるよう配慮された新たな権利だ。この権利により、家屋の所有権を取得せずに、家屋(敷地の利用権を含む)を無償で使用・収益することが可能となる。
配偶者居住権の設定要件
配偶者居住権を設定するためには、以下の要件を満たす必要がある。
- 配偶者が相続開始時に被相続人の家屋に居住していたこと(入院中の場合でも、退院後に居住予定であれば可)。
- 被相続人がその家屋を配偶者以外の者と共有していないこと。
配偶者居住権の活用例
典型的な活用例として、以下のケースが挙げられる。
- 被相続人である夫の居住用土地家屋について、所有権は先妻との子が相続し、終身の居住権は後妻に与える。
このような場合、後妻は老後の居住場所を確保しつつ、所有権を取得しない分だけ生活資金を多く確保できる。ただし、修繕費や固定資産税等の通常必要な費用は配偶者が負担し、増改築や第三者への使用には所有者の承諾が必要だ。
登記と相続税評価額
配偶者居住権を設定した場合、権利の登記が必要となる。登記がなければ第三者に対抗することができない。
相続税の計算では、土地家屋の評価額が所有権と居住権の二つに分けられる。例えば、配偶者居住権設定前の土地家屋の評価額が4,000万円であれば、所有権2,000万円、居住権2,000万円のように区分される。評価方法は、家屋の経過年数や配偶者の年齢に応じた余命年数に基づき、相続税法で規定されている。
配偶者居住権の節税効果
配偶者居住権は、存続期間を特に設定しない場合、通常は配偶者の死亡時に消滅する。この消滅が節税効果をもたらす事例を以下に示す。
ケース① 配偶者居住権設定なし
- 一次相続(夫死亡)
- 妻:土地建物4,000万円、現金3,000万円を取得
- 子:現金7,000万円を取得
- 二次相続(妻死亡)
- 子:土地建物4,000万円、現金3,000万円を取得
ケース② 配偶者居住権設定あり
- 一次相続(夫死亡)
- 妻:配偶者居住権2,000万円、現金5,000万円を取得
- 子:土地建物2,000万円、現金5,000万円を取得
- 二次相続(妻死亡)
- 子:現金5,000万円を取得
ケース②では、二次相続における相続財産が2,000万円少なくなるため、相続税の節税効果が期待できる。
小規模宅地等の特例との関係
被相続人の居住用土地に関しては、330㎡を限度に評価額を80%減額する「小規模宅地等の特例」が適用される。
- 妻が土地を相続する場合:80%減額の適用あり。
- 配偶者居住権を設定する場合:敷地利用権に対して80%減額が適用される。
ただし、敷地利用権の面積は、土地全体の相続税評価額に対する敷地利用権の評価額割合を乗じて算出する必要がある。
まとめ
配偶者居住権は、相続税の節税効果を得つつ、配偶者の居住と生活資金の確保を両立する有効な手段だ。ただし、費用負担や登記手続きなどの要件を正確に把握し、適切に活用することが求められる。