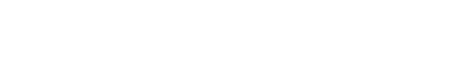2024年10月から、特定労働者(70歳未満で、厚生年金保険法の適用除外とならない一定の者)が51人~100人規模の会社においても、社会保険(厚生年金保険、健康保険)の適用範囲が拡大される。この改正により、これまで社会保険適用外だったパート・アルバイト労働者も新たに被保険者となるケースが増加する。また、2024年12月現在、「106万円の壁」の廃止も議論されている。
社会保険適用範囲拡大のポイント
これまでは、51人~100人規模の会社において、フルタイムの4分の3未満の労働者は社会保険の適用除外だった。しかし、今回の改正では、4分の3未満の労働者であっても、以下の全ての条件を満たす場合、社会保険の被保険者となる:
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 1月当たりの報酬が88,000円以上 「106万円の壁」
- 学生でない
これにより、企業はパート・アルバイト労働者の社会保険負担が増加し、運営に大きな影響を受ける可能性がある。
働き控えによる影響と対応策
社会保険の適用拡大により、パート・アルバイトが「106万円の壁」を意識して働き控えを行い、人手不足がさらに深刻化するリスクがある。これを回避するための具体的な対応策として「会社分割」がある。
会社分割による対応策
会社分割を活用することで、労働者数を50人以下へと調整し、社会保険の適用拡大を回避することが可能だ。もちろん、事業内容や組織体制を踏まえた経済的合理性のある会社分割であることは必要だ。本記事では、会社分割のメリットや留意点について詳しく解説する。
会社分割の概要
会社分割とは、企業が保有する事業の一部を分割し、新たに設立した法人や既存法人に承継させる手法である。以下のポイントが重要となる:
- 資産・負債・契約関係の包括承継:分割事業に関する資産や負債、契約関係などは、新法人に包括的に承継される。
- 契約再締結の不要性:通常、契約書に会社分割の承継禁止が明記されていなければ、契約再締結は不要。
- 手続き期間:債権者保護手続きなどの会社法上の手続きに約2か月が必要。
- 従業員の承継:労働契約承継法により、通常、従業員の同意なく承継可能。退職所得控除の算定における勤務年数は継続される。
会社分割の留意事項
- 金融機関との調整:借入金がある場合、金融機関との調整が必要。重畳的債務引受を利用すると手続きが円滑に進む。
- 許認可の承継:許認可の承継が可能なものもある。承継不可となる場合は、新法人が許認可を取得した後に吸収分割を行うことで事業継続が可能となる。
課税上の取扱い
- 税負担の軽減:完全支配関係にある法人間の会社分割であれば、株主への金銭交付がない場合は、法人税や所得税が課されない。また、会社分割は包括承継とされるため、消費税は課されない。
- 消費税の注意点:納税義務や簡易課税の判定は、分割承継法人の課税売上高だけでなく、分割法人の課税売上高も含める必要。
- 不動産流通税:不動産の移転が伴う場合、登録免許税や不動産取得税が課される。なお、不動産取得税は、非課税要件を満たせば、課されない。
届出
会社分割後には、主として以下の届出が必要となる:
- 期中損金算入に関する届出書:分割法人で、分割の日以後2か月以内に提出。
- 給与所得者異動届出書:従業員の住民税の適切な特別徴収のために提出。
- 社会保険関連届出書:分割法人、分割承継法人で「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」などを提出。
社会保険制度改正の展望
2024年12月現在、さらなる社会保険適用拡大が議論されている。
- 「106万円の壁」の廃止:2026年10月に廃止予定。
- 企業規模要件の廃止:2027年10月に特定労働者50人未満の企業についても、適用除外が撤廃予定。
これにより、適用範囲拡大が進む一方、企業への支援制度の創設も期待されている。企業は早めに対応策を検討し、適切な運営体制を整えることが重要だ。
まとめ
社会保険適用範囲の拡大は、多くの企業にとって負担増加を伴うが、会社分割などの戦略的対応を行うことでリスクを軽減できる。法改正の動向を注視しながら、自社の状況に応じた適切な対応を検討することが求められる。具体的な手続きについては、社会保険労務士、税理士、司法書士など専門家のアドバイスを受けることを推奨する。