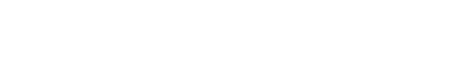役員社宅を役員に低い対価で貸与する場合、適正な賃貸料との差額は経済的利益と見なされ、給与課税の対象になる。しかし、役員から通常の賃貸料相当額を徴収していれば、その差額は、給与課税の対象外となる。借上社宅の場合、この賃貸料相当額は少なくとも、会社が家主へ支払う賃借料の50%以上とする必要がある。
ただし、借上社宅の床面積が99㎡以下(木造は132㎡以下)の小規模住宅であれば、以下の算式で計算される賃貸料相当額を役員から徴収すればよい。この額は通常、会社が家主へ支払う賃借料の50%よりも低くなることが多い。
本記事では、市町村における閲覧制度を活用することにより、役員社宅(小規模住宅)の役員本人負担を軽減する方法について記載する。
【賃貸料相当額の算式】
下記の合計額が、通常の賃貸料相当額となる。
- その年度の家屋の固定資産税の課税標準額 × 0.2%
- 12円 × 家屋の総床面積(㎡) / 3.3㎡
- その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%
固定資産税の課税標準額の確認方法
借上社宅の場合、この「固定資産税の課税標準額」の確認が難しいため、実務上では小規模住宅であっても、会社が支払う賃貸料の50%を徴収しているケースが多い。
固定資産税課税標準額は、毎年4月に各市町村から賃貸人に送付される固定資産税課税明細書を確認することで把握可能である。賃貸人に開示請求すればよいが、賃貸人が所有の他の土地や家屋の情報も含まれるため、実務上困難な場合がある。
地方税法では、固定資産課税台帳の閲覧が賃借人(借地人・借家人)にも認められており、不動産所在の各市町村において、賃借物件の情報を一年中閲覧することが可能である。固定資産課税台帳には課税標準額と固定資産評価額などが記載されている。
家屋の固定資産評価額は課税標準額と同額であることが多いが、土地に関しては住宅用地特例や負担調整措置の適用により、評価額と課税標準額が異なる場合があるため、算定の際には注意が必要である。
福岡市での閲覧手続き
福岡市では、固定資産課税台帳の閲覧の際に、以下の書類の提示が求められる:
- 賃貸借契約書および賃借料の直近の領収書(通帳コピーなど支払った内容が分かる資料 ※:事前確認要)
- サブリース契約の場合は、転貸借契約書と直近の領収書に加え、家主とサブリース会社との原契約書および領収書の写し
- 法人印および代表者の職印
また、有料となるが、固定資産課税台帳の写しの交付も可能である。必要に応じて固定資産評価証明書を取得することもできる。
閲覧対象の物件が一棟所有のマンションである場合、台帳の情報は一棟全体の記載となり、各専有部分に按分計算する必要がある。この場合、窓口で計算方法を確認しておくと良い。
留意点
- 床面積240㎡を超える住宅や**特別な設備(プール等)**を備えた住宅は、「一般に貸与される住宅等」とみなされない。会社の事業用資産を役員が専属的に利用しているとして、会社が家主へ支払う賃借料と役員負担額の差額が、給与課税の対象となる。
- 別契約の駐車場費用を会社が負担していないか確認する必要がある。
- 固定資産税評価額は通常3年ごとに見直され、課税標準額も変動するため、適正な徴収額の算定を定期的に行うことが重要である。
- 新築物件で、固定資産課税台帳を閲覧する年度の1月1日時点で完成していない場合、固定資産課税台帳の閲覧はできない。
まとめ
役員社宅(小規模住宅)を利用する場合、適正な賃貸料相当額の設定と固定資産税課税標準額の把握が重要である。閲覧制度を活用することで、正確な課税標準額を把握し、役員負担を適切に設定することができる。適正な手続きを行うことで、役員への給与課税リスクを軽減し、効率的な経済的利益の享受を目指そう。