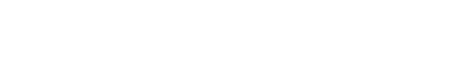法人化する事業の選定
個人事業の所得税の負担が大きく、法人化すべきかについての相談は多く寄せられる。
所得税・住民税は最大55%の税率で課され、さらに、多額の納税を果たし財産を形成したにもかかわらず、死後には、その残された財産には相続税が最大55%の税率で課されるため、当然に法人化は検討すべきだ。法人の場合、800万円までの所得は実効税率約23%、超過所得は約33%とされる。
この場合、相談される前提として、個人事業を廃止し全てを法人へ移転させるとのケースが多い。
ただ、複数の事業があるのであれば、利益が多い事業のみを移転させれば、十分に納税の最適化は図られる。
利益が少ない事業は、手間とコストをかけて法人へ移転させる必要はない。
特に顕著な事例としては、不動産賃貸業であり、利益が出ていない賃貸物件を移転しても、税額軽減効果は低く、移転時に譲渡所得税、登録免許税、不動産取得税の負担が大きいだけである。
法人化する場合には、費用対効果を考え、どの事業を移転させるか選定することが重要である。
また、法人化検討の一つの目安としては、経験上、所得税の課税所得が1,000万円を超えているか否かとなろう。
親族への所得の分散
一人に所得が集中すると、所得税は超過累進税率のため、非常に納税額が高くなる。しかし、法人化により親族へ役員報酬を支給すると、所得分散が図られ、納税額が抑えられる。
個人事業主でも、同一生計親族へ青色専従者給与を支給することは可能であるが、専従していることが必要であったり、届出を提出の上、同一業務で第三者へ支給するとどのくらいかという相場を意識しなければならない。また、資金繰りを考慮して、支給日に給与を支給しないといったことは認められない。
一方、役員報酬であれば、取締役としての経営への貢献をもって支給額を設定できる。専従は要件とはならない。一時的な報酬の未払いが生じても、役員賞与を除き、損金算入は認められる。役員でなく、使用人であれば、第三者へ支給するとどのくらいかという相場があることには注意が必要だ。
納税の繰り延べと退職金支給
個人事業主の場合、納税の繰り延べとなる節税対策は少ない。生命保険に加入しても、最大12万円の控除しか受けられない。
一方、法人の場合、生命保険へ加入すると、支払時は4割損金算入となり、将来的な解約時に、返戻金と配当金を合わせると100%近い返戻率となる商品も見受けられる。
また、航空機リース、船舶リースといった節税商品も認められており、1億円出資した場合、1年目に7千万円の損金算入、2年目に3千万円の損金算入といた商品が一般的である。約10年後に100%以上で返還され、その際、全額益金算入となるが、退職金の支給により損金算入し、所得を相殺させることも可能だ。
退職金の支給は、個人事業主の場合、本人、同一生計親族へは、一切認められないものである。
退職金は、勤続年数に応じた退職所得控除が認められるし、所得税・住民税率は、最大でも27.5%と低いことも特徴である。
また、社会保険の支払いも必要ない。
法人が複数あれば、複数回の退職金の支給を受けることが可能だ。しかし、勤続年数が5年以下であれば、最大27.5%の税率ではなく、通常とおり最大55%の税率となることや、5年以内に他社での退職金の支給実績があれば、退職所得控除に一定の制限が設けられる点は留意すべきだ。さらには、そもそも複数法人を営む経済的合理性がなければ、同族会社の行為計算の否認の規定が適用されるので、この点も注意が必要である。
個人事業の不動産所得であれば、中小企業倒産防止共済による必要経費への算入は認められないが、法人化した場合、損金算入が認められる点も大きなメリットである。個人事業が事業所得であれば、中小企業倒産防止共済による必要経費への算入は可能であるし、法人化した場合、さらに追加で中小企業倒産防止共済に加入ができる。掛金は全額損金加入で、40か月以上加入していれば、100%以上返還される点が非常に優れた制度だ。
納税の繰り延べに関して、出口で課税されるとして積極的な実行をしない事業主もいるが、個人的には、キャッシュフローに支障を及ぼさない範囲で実行すべきと考える。
例えば、ある年度に1億円の納税をしたとして、それから5年後に赤字が続いたとしても、1億円を納税した貢献への救済制度は一切存在しない。現行制度では、納税年度の翌年度に赤字が発生した場合にのみ繰り戻し還付制度が存在するだけである。自身と家族のみならず、従業員の雇用を守るためには、納税に対する一定の対策は必要であろう。
消費税の抑制
消費税は、「売上にて預かった消費税」から、「仕入れ等にて支払った消費税」を、差し引いた残額を納付するものである。
ただ、売上が5,000万円以下の小規模事業者の場合、簡易課税制度という消費税の納税方法が認められている。
これは、「仕入れ等にて支払った消費税」に関して実際の支払い額ではなく、「売上にて預かった消費税額」の40%~90%を「仕入れ等にて支払った消費税」とみなすものである。極端な話、実際の「仕入れ等にて支払った消費税」がなくとも、この規定により消費税額の計算上、「仕入れ等にて支払った消費税」を控除することができ、消費税額を抑えられるケースがある。
判定の年度は、2年前の売上が5,000万円以下であるか否かとなるため、法人設立1期目、2期目は、2年前の売上がないため、事業の規模に関わらず、簡易課税制度の適用が可能となる(新設会社分割を実行した場合を除く)。
3年目以降も、個人事業主の売上4,000万円、法人の売上4,000万円といったように、各々の事業において、簡易課税制度の適用が可能となるケースも想定される。
※:令和8年9月30日を含む課税期間までは、インボイス制度に係る経過措置(2割特例)の適用も受けられる。
相続税の抑制
冒頭、個人事業主は、所得税・住民税が最大55%で課され、死後に、残された財産に最大55%の相続税が課されると記載した。
個人事業主として、利益を得て所得税・住民税を納付したとしても、その残額を生活資金として使い切らなければ、毎年財産が蓄積される。死後に残った財産に相続税が課される。
このため、次世代へ財産を残すことを考えれば、法人化を実行し、高い所得税率による納税から、低い法人税率への切り替えを図り、法人内により多くの蓄積財産を残す。法人の株主を個人事業主以外の次世代とすることより、相続開始前に実質的な財産の承継が可能だ。
また、株主が個人事業主を含む場合であっても、相続税は抑制される。
個人で所有する1億円の現預金は、相続税評価額としても1億円の評価となる。
一方、法人化により法人内に蓄積された純資産1億円は、相続税評価額としては1億円とならない。法人の株式としての相続税評価額となり、非上場株式に関する財産評価基本通達により算定され、法人がペーパーカンパニーである場合を除き、通常、1億円より大幅に低い評価額となる。
社会保険の検討漏れに注意
多くの法人化の提案書において、親族へ役員報酬を支給することにより、所得の分散化が図れ、所得税の負担が下がる旨、記載されている。誤りではないが、法人は、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が必須となり、支給する役員報酬に対して、15%の本人負担、15%の法人負担があるため、想定より手取りが少なくなるケースや、法人化することにより個人事業時よりも手取りが少なくなるケースもありうる。
社会保険に関して、有利となるケースとしては、法人化した後も、個人事業主として一定の所得を確保しつつ、役員報酬も一定額支給することにより、健康保険・厚生年金へ加入し、高額な国民健康保険からの切り替えを図ることが有効だ。後、役員報酬(給与所得)にこだわる必要がなく、貸付け(不動産所得、雑所得)として支給を受けるものがないかについても検討のポイントとなる。