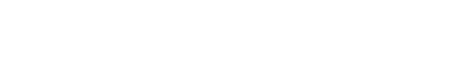令和7年度税制改正大綱が公表され、会社に企業年金の制度がない未加入者が、iDeCo(個人型確定拠出年金)へ拠出できる限度額が39,000円(月額)引き上げられる見込みだ。企業年金の拠出限度額も7,000円(月額)引き上げられる。
また、確定拠出年金の一時金支給に加えて会社からも退職金の支給を受ける場合の、退職所得控除の調整規定が一部見直しされる。
確定拠出年金(企業型、個人型)の拠出限度額の改正内容
| 加入状況 | 現行拠出限度額(月額) | 令和7年度税制改正案(月額) |
| 企業年金に加入している場合 | 55,000円 | 62,000円 |
| 企業年金未加入者のiDeCo | 23,000円 | 62,000円 |
| 自営業者のiDeCo | 68,000円 | 75,000円 |
現行制度では、企業年金の拠出限度額(月額)は55,000円だが、会社に企業年金制度がない未加入者のiDeCoへの拠出限度額(月額)は23,000円と大きな差がある。令和7年度税制改正では、企業年金の拠出限度額および、企業年金未加入者のiDeCoへの拠出限度額が、共に62,000円へ引き上げられる。
多くの中小企業では企業型確定拠出年金を導入しておらず、その従業員は高齢期の生活の安定のため、iDeCoを利用して老後資金を確保する必要がある。
また、自営業者などについては、iDeCoの拠出限度額(月額)が、68,000円から75,000円へと引き上げられる見込みだ。
確定拠出年金の仕組みと特徴
確定拠出年金とは、個人又は事業主が拠出した掛金とその運用収益を基に将来受け取る年金額が決まる制度だ。加入者自身が株式や債券、定期預金などの運用商品を選んで運用する。一度拠出した掛金は、原則として老齢給付金の支給を受けるまで引き出せない点には留意が必要である。
確定拠出年金の税務上のメリット
確定拠出年金は拠出時、運用時、給付時の3つの段階で税制優遇が設けられている。
- 拠出時:個人が拠出する掛金が全額所得控除の対象となる。事業主が拠出する掛金は損金算入の対象となる。
- 運用時:運用益は非課税。
- 給付時:年金または一時金として受け取る際に優遇措置がある。
給付時の税制優遇
- 年金として受け取る場合:雑所得として扱われ、公的年金等控除が適用される。下記に65歳以上の場合の控除額を示す。
- 年金収入330万円以下では110万円が控除額となる。
- 330万円超~1,000万円以下では収入に応じて算定(例:収入500万円で控除額143.5万円)。
- 1,000万円超では一律195.5万円の控除となる。
- 一時金として受け取る場合:退職所得として退職所得控除が適用される。
- 勤続年数20年以下のとき: 40万円 × 勤続年数(最低80万円)
- 勤続年数20年超のとき: 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 – 20年)
確定拠出年金一時金と退職金の重複における注意点
確定拠出年金一時金と会社から退職金を受け取る場合、退職所得控除の計算で以下の点に注意が必要だ。
- 同じ年に受給の場合:退職所得控除の勤続年数には、加入年数と勤続年数のうち長い方が適用される。
- 受給年が異なる場合:
- 退職金支給年前年以前9年内に確定拠出年金一時金を受け取ったとき(現行4年内):重複年数部分の退職所得控除が減算される。(令和8年1月1日以後に確定拠出年金一時金の支給を受けた場合は、9年内が適用)
- 確定拠出年金一時金支給年前年以前19年内に退職金が支給されたとき:重複年数部分の退職所得控除が減算される。
- 退職金が高額の場合:会社からの退職金額が退職所得控除額を超えるとき:確定拠出年金一時金に退職所得控除が適用されない場合がある。
確定拠出年金利用時の留意点とまとめ
確定拠出年金は税制優遇がある一方、注意すべき点も存在する。
- 退職金との重複:確定拠出年金一時金と会社から退職金を受ける場合、退職所得控除が調整される可能性がある。
- 改正の動向:退職所得控除が、今後の税制改正で減少の可能性について、議論されている。
確定拠出年金は老後資金の形成に有効な手段だが、退職金との調整や税制改正の影響を考慮する必要がある。最新情報を把握し、適切に制度を活用することが重要である。